
第18回のご報告
2009年12月18日(金)の午後7時から第18回目の場がスタートしました。経営者、NPO職員、研究者、ビジネスパーソン、建築家、研修講師、市民メディアプロデューサーなど海士町や離島に心寄せる20名の場づくり人が集い、ゲストからの差し入れに舌も躍らせつつ、2009年を締めくくる対話を楽しみました。
(感謝!)
報告書はこちら
海士町は、東京から約900km離れた日本海に浮かぶ人口2427人の隠岐諸島の一つの島です。古くから半農半漁が根付いており、豊富な海産物がとれるため釣り人にも愛され、透明度が高い海は、日本海側で初めてのダイビングスポットとなりました。
近年では人口流出による少子高齢化と財政破綻の危機の中にあって、独自の改革手法と若者を引き寄せ育てる新たな人づくりの取組によって、注目が集まっています。
◎ 第18回テーマ:「離島と東京を結ぶ」
☆ゲストスピーカー (30分) 佐藤 喬さん(さとう たかしさん)
(海士(あま)町観光協会職員)
佐藤さんから気さくに「皆さんどうぞ、海士町のイカを召し上がりながら・・・」でスタートした場。さすが、行商人。みんなの頬が緩みました。フムフム・・・。
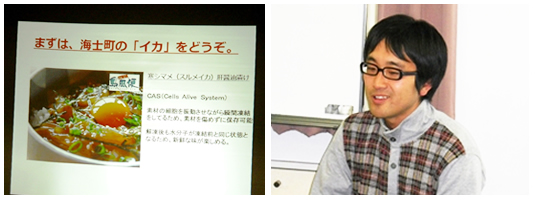
佐藤さんは、秋田県出身。33歳、早稲田大学大学院理工学研究科を中退の後、テレビ番組のディレクター(NHKのドキュメンタリー)や広告のプランナー&ライターを経て、
2009年から海士町観光協会の研修生として「離島キッチン」を立ち上げました。
そのきっかけは、2009年2月に海士町が「行商人募集します!」の求人広告を掲載。
全国から87名の応募があり、2名が研修生として採用され、佐藤さんは、東京の行商人となりました。
2009年のミッションは、「やりたいことは、自分で見つけること」。
そこで、離島専門チャンネル設立に向けて、住民からの出資によるCATV設立が大きな目標。出資していただく金額に応じて、利益を分配し、離島の情報発信・ショピング・旅行などを多ジャンルにわたる業務を行っていくことを構想。
しかし、まだまだ時期尚早ということで、まずは「食」をテーマにしようと海士町だけではなく、他の離島の食事も提供し、全ての離島のPRを担えるような車をつくり、「離島キッチン」として、移動販売を始めました。
海士町のさざえカレー、ふくぎ茶、奄美大島の奄美鶏飯、種子島の安納焼いもなどの他、家島の天然あなご丼を商品開発中。試食させていただいた寒シマメ(スルメイカ)の肝醤油漬けは、CAS(Cells Alive System)という素材の細胞を振動させながら瞬間凍結した素材を傷めず保存する方法で、解凍後も新鮮な味が楽しめるという逸品でした。
「離島キッチン」の役割を5つ考えています。
①離島の食事の提供、②離島の観光情報の提供、③新商品のマーケティング、④島の求人情報の提供、⑤固定店舗の設立準備により、全国の離島の方々に、「離島キッチン」を自由に利用してもらい、 <場所の創造> <仕事の創造> <ライフスタイルの創造> をしていきたいです。
これからは、都会と離島というような2地域に住むというライフスタイルが面白いと思います。実際、島前高校の魅力化プロジェクトなど若者が集ってきています。
2010年に固定店舗をオープンさせ、段階的に離島専門チャンネルを東京・海士町に設立していくという計画を語ってくださいました。

◎ 人むすびカフェ
ファシリテーター:角田 知行さん
「人むすびカフェ」は、ワールド・カフェの手法を用いて、ひとつのテーマから連想されるアイデアを出し合い、初めての方とでも楽しく話し合いをしています。テーブルを回っていくことにより、多くの人と対話を深められます。

今回のお題は、「新しいことを始める時、そこにあるのは何でしょうか?」
こんなご意見がありました。
・ 普段見れない世界、今の生活にないもの
・ 一歩踏み出す勇気
・ 志(どうなりたいかのビジョン)と偶然(セレンディピティ)から気付きと成長が生まれる
・ 一人では何もできない、考え方がバラバラ ⇒ 合意がいる
・ 走りながら考える新しいライフスタイル、ビジネスモデル、など
 ◎ 最後に今日の気づき、キーワードを感想に残し、望年会に向かいました。
◎ 最後に今日の気づき、キーワードを感想に残し、望年会に向かいました。
